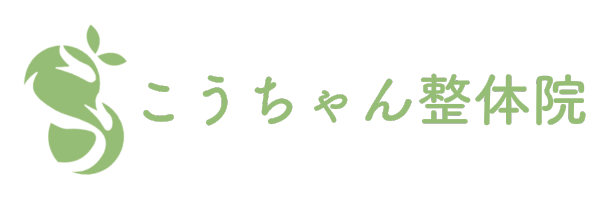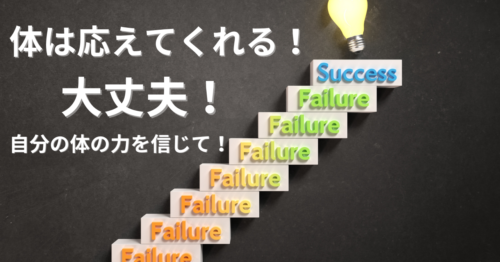こんにちは。
日南市のこうちゃん整体院・院長の吉本幸司です。
首のこり、首の痛みがあって、ほったらかしにしていませんか?
実は、首のこり(首の痛み)が「うつ病」の原因になるということを知りました。
首のこり(首の痛み)が原因で引き起こされるうつ病を「頚性うつ」と言うそうです。
頚性うつとは?

実は、うつ(気分障害)の多くは首・自律神経の治療で 改善させることが可能です。
松井医師は多くの臨床例より、首の筋肉異常によって発症する不定愁訴から「うつ」を発症することを突き止めました。そして、このことを「頚筋性うつ」と呼びました。
首の筋肉異常が引き金となる頚筋性うつは「頚性うつ」あるいは「首からうつ」と呼ぶこともできます。
https://tokyo-neurological-center.com/blog/350/
首のこりや肩こりは、これぐらい大丈夫と我慢しがちですが、
対処が遅くなると、大事になりがちです。
もうこれ以上我慢できないと感じる前に対処することをお勧めいたします。
頚性うつの原因をつくる首こり(首の痛み)はどんなことをするとなるの?
首のこりは、長時間の下向きの状態や上向きの状態など、同じ姿勢が持続した時、
首の筋肉が縮こまってかたくなった状態をいいます。
頚性うつをつくる原因が首のこりなので首を長時間同じ姿勢での持続状態が続き、
首のこり(首の痛み)が強くなると、頚性うつへと移行していきます。
下記のことをやることが多いと首のこり(首の痛み)が強くなる傾向があります。
・2時間以上の車の運転
・美容師
・飲食店で料理を作っている
・整骨院・鍼灸院・整体院で施術をしている
・2時間以上スマホを使っている
・2時間以上PC作業をしている
これらのことは首こりと同時に肩こりをつくる原因にもなっています。
肩こりもうつ病の原因になる?
寒い日と暖かい日の気温差が5℃以上になると、身体に影響を及ぼしてきます。
その1つが肩こりです。
ただ、肩こりだけで終わればよいのですが、肩こりはいろんな症状を巻き込んできます。いわゆる合併症というものですね。
今日は、肩こりについて深めていきたいと思います。
肩こりがすごい!イタイ!という方が増えてきています。


肩こりがひどくなると、よく出てくる症状が、
頭痛、歯の痛み、目の痛みです。
そして、もう少し症状が進んでいくと、眠気も出てくるみたいです。
今、どのあたりまで痛みが進行していますか?
肩こりは精神的にもダメージを与える?つまり、肩こりはうつのきっかけをつくる!

これは、意外と思われるかもしれませんが、肩こりはうつの症状を悪化させるきっかけをつくります。
肩こりをほったらかしにしておくと、うつ病へと進行していくのですね。
うつ症状が出てくると、前かがみになりがちです。
猫背になって、頭が前に出てきます。
結果、肩に負担がかかり、肩こりを引き起こす原因をつくります。
また、逆に考えることもできます。
肩こりになると、首から上、つまり脳に行く血液の流れが滞り、脳細胞へ運ぶ血液の量が減ってしまいます。
脳細胞が酸欠状態になるので、これが原因で感情が不安定になります。
別な言い方をすると、自律神経の働きに狂いがおこるということですね。
肩こりが悪化すると、精神的にも病んでいきます。
これが、肩こりは万病の元といわれる理由です。
肩こりは、すべての病気の出発点です。
今の症状、病気、うつ症状を治したいと思ったら、肩こりを治すことが先なのかもしれませんね。
まとめ
肩こりは万病の元。
腰痛も頭痛も、首の痛みも、膝の痛みも坐骨神経痛も
すべて、肩こりに原点があります。
肩こりを治して、次へと進んでいきましょう。
一番の早道かもしれません。